「上手にコミュニケーションが取れたり、周りとわいわい楽しめたりしていたら絵なんて描いてませんよ」
わたしは仕事がらいわゆるクリエイターと呼ばれる人たちと接することが多いのだけれど、とても優秀なアートディレクターの一人がそんなことを言っていた。彼女はディレクターとしても優秀で、もちろん周囲と円滑にコミュニケーションもでき、なんら不都合はない。チームメンバーとも楽しく仕事ができているし、仲の良い人もいるように見える。ただ、決してそうしたことが得意ではなく、中高生の頃は特に、上手にできる方ではなかったようだ。
絵の上手い人というのは大勢いる。でも彼女の言葉に秘められた絵の「動機」は極めて強い。いい絵を描きたくて始めるのではない。世界とつながるために絵しかないから絵を描く。
わたしの周りには絵の上手な人がとても多い。プロも大勢いる。プロか否かに関わらず、その「上手」にはいろいろな種類がある。もちろん職種によって求められる「上手さ」が異なるという事情もあるけれど、やはり根っこにどんな動機があるかというのは表層に出てくる表現を大きく左右するように思う。
そう思って我が身を振り返る。わたしにはそういう動機があったろうか。
幼い頃から表現は好きだった。歌を歌うのが特に好きだった。わたしはおそらく、外から見るとコミュニケーションが苦手な方には見えないだろう。小学生の頃から学級委員をやったり学級会でパフォーマンスを披露したり、目立つことを積極的にやっていた。今になって思うと、加減がわからずに目立ちすぎていた気配もある。わたしにはそれが、世界とつながる方法だった。
中学生の頃、ありがちだが大人を憎悪した。いわゆる中二病的な症状だけれど、わたしはそれが極端に強かったように思う。重症中二病だったわけだ。大人は汚らわしく、ひたすら憎いものだった。世界は欺瞞に満ち、社会はその巨悪の根源だった。そして自らの身体は否応なく大人に近づいていった。そのことが我慢ならなかった。このまま自分も憎い大人になってしまうのかと思うと、もはや死ぬ以外にそれを避ける方法はないとさえ思った。
そして音楽を始めた。音楽は幼い頃からやっていた。歌も好きだったし、楽器も習わせてもらっていた。小学生の頃、わたしにとって音楽はファン・トゥ・ミュージック。楽しければいいものだった。中学に上がり、社会を憎悪したわたしにとって、音楽は武器であり癒やしとなった。本当に、それがなければ死ぬというようなものだった。
そのまま音楽で生きていきたいと思って活動を続けてきたけれど、うまくはいかなかった。それが成功していたらきっと、わたしは小説など書いていないだろう。
いつしか社会への憎悪は薄まり、自分は自分が憎悪したタイプの大人にはならずに済んだと思えるようになった。こういう生き方があったのかと、ある種の精神的な安定を得ることができた。それはきっと「自信」に近いものだと思う。それを手に入れたのは25歳を過ぎた頃だった。
わたしにとって表現は相手を滅ぼすための武器ではなく、世界に問を投げるためのものに変化していた。相変わらず内側には、問わねばならないものが渦巻いている。誰に求められておらずとも、投げねばいられない問が次から次に湧き上がってくる。
音楽しか無かったわたしはいろいろな趣味を通じて他の表現も学んだ。巧拙はいろいろある。手を出しすぎてどれも中途半端である感じも否めない。でも幅が広がったことで、できることは間違いなく増えた。
2017年、自分の中のある区切りをきっかけに小説を書き始めた。そんなわたしには思春期にどうしようもなくて書かれる小説のようなものは書けないだろう。でもいくつかの表現を経てここへたどり着いたわたしは、わたしの中にある得体のしれないものを解き明かすのにもっとも適した表現はこれなのではないかと思っている。もはやまったく若くはないわたしではあるけれど、新鮮な気持ちでこの表現と向き合っているつもりだ。
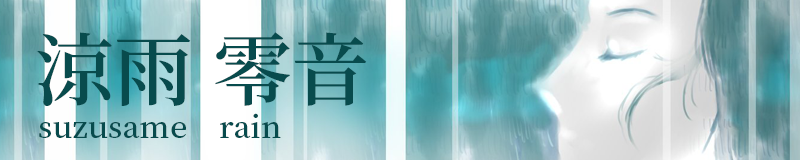



コメント